保育園は子どもの命を守る大切なステップです
2018年8月22日
働く親の「困った」に応える保育園ファンド
代表の河村です。
昨日は、子どもの自殺に関する勉強会に出席しました。
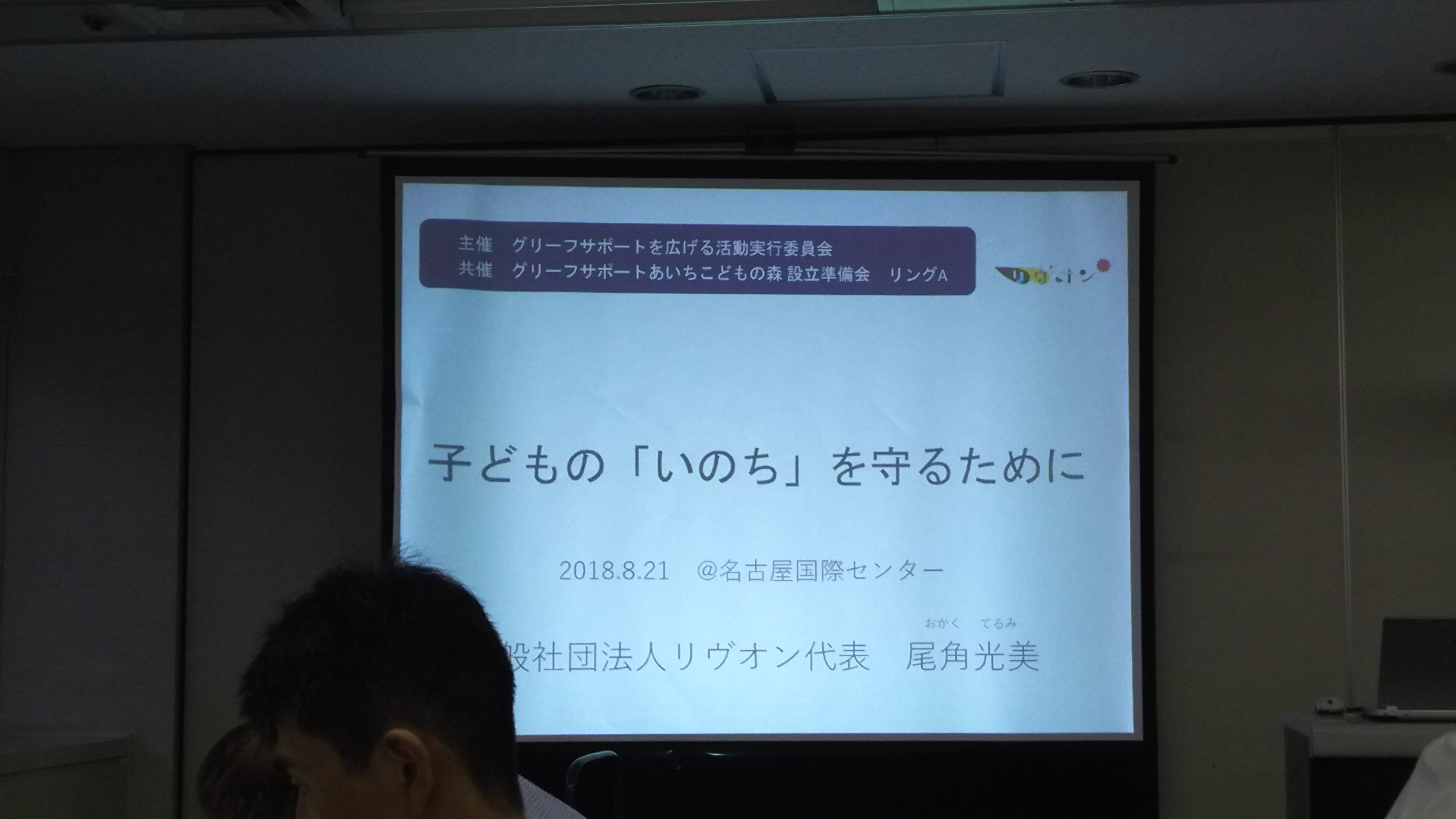
どちらかというと、お坊さん、学校の先生やソーシャルワーカーなどの職種の方が中心だったのですが、ちょっと驚きもありました。
10歳~14歳の死因順位を質問されたときのことです。参加者(50名くらい)で挙手をするのですが、その結果はというと・・・
①事故・・・8名
②がん・・・1名(っていうか私だけ)
③自殺・・・多数
です。で、実際の順位はというと
1位 がん
2位 自殺
3位 事故
でした。
いや、お坊さんはともかく、学校の先生たち、いくらなんでも情報が足りてなくない??と思いました。
帰宅後、同じ質問を妻にしたら「自殺」を選びました。その理由を聞くと「だって自殺予防のセミナーでしょ」との回答。古い表現ですが、こういうのも「忖度」っていうんでしょうか(笑)
セミナーの感想は、なるほどアプローチが違うと視点が変わるなぁというものでした、
今回の主催は、親を自殺で亡くした子どもたちが始めた活動です。自殺を経験した遺族という観点から、子どもたちの命を守ろうというものでした。つまり、どう育ってきたのか、というよりも、これから、どう生きていくのかに主眼があるという感じですね。
一方で、保育事業者の私の視点は、愛着形成により自己肯定感(自分は大切な存在)を高め、自殺を予防しようという考えです。この考えはとても重要なのですが、一方で、成長は不可逆的ですから、自己肯定感が乏しい子どもの自殺防止にはつながりません。
実際に「死にたい」と思った子どもは「自殺は命を粗末している」という考えを持っていないというアンケート結果が紹介されました。自分の命を大切に思っていない(自己肯定感が低い)ことが分かります。
これから育っていく子どもたちには自己肯定感を高めるを私たちの保育園があるとして、今、苦しんでいる子どもにどう接していくのか、大きな課題だと思いました。
昨日は、子どもの自殺に関する勉強会に出席しました。
どちらかというと、お坊さん、学校の先生やソーシャルワーカーなどの職種の方が中心だったのですが、ちょっと驚きもありました。
10歳~14歳の死因順位を質問されたときのことです。参加者(50名くらい)で挙手をするのですが、その結果はというと・・・
①事故・・・8名
②がん・・・1名(っていうか私だけ)
③自殺・・・多数
です。で、実際の順位はというと
1位 がん
2位 自殺
3位 事故
でした。
いや、お坊さんはともかく、学校の先生たち、いくらなんでも情報が足りてなくない??と思いました。
帰宅後、同じ質問を妻にしたら「自殺」を選びました。その理由を聞くと「だって自殺予防のセミナーでしょ」との回答。古い表現ですが、こういうのも「忖度」っていうんでしょうか(笑)
セミナーの感想は、なるほどアプローチが違うと視点が変わるなぁというものでした、
今回の主催は、親を自殺で亡くした子どもたちが始めた活動です。自殺を経験した遺族という観点から、子どもたちの命を守ろうというものでした。つまり、どう育ってきたのか、というよりも、これから、どう生きていくのかに主眼があるという感じですね。
一方で、保育事業者の私の視点は、愛着形成により自己肯定感(自分は大切な存在)を高め、自殺を予防しようという考えです。この考えはとても重要なのですが、一方で、成長は不可逆的ですから、自己肯定感が乏しい子どもの自殺防止にはつながりません。
実際に「死にたい」と思った子どもは「自殺は命を粗末している」という考えを持っていないというアンケート結果が紹介されました。自分の命を大切に思っていない(自己肯定感が低い)ことが分かります。
これから育っていく子どもたちには自己肯定感を高めるを私たちの保育園があるとして、今、苦しんでいる子どもにどう接していくのか、大きな課題だと思いました。